皆さんが毎日当たり前のように食べている「パン」。「菓子パン」「総菜パン」など様々なパンが存在しますが、そんなパンについての知識を皆さんはどれの位ご存じでしょか?当たり前のように食べているからか、ほとんど知らない方もいるのではないでしょうか?
今回はそんな「パン」について簡潔にではありますが、お話ししていこうと思います。
「パン」の定義
そもそも「パン」とはどんな食べ物を指すのか、改めて知っていきましょう。
「パン」とは、「穀物粉(小麦粉やライ麦粉)」に水や酵母、塩などを加えて作った生地を「発酵」によって膨らませて焼いた食べ物のことを指します。
種類によっては、砂糖や卵や油脂、その他の副原料を加えて生地を発酵させて焼いた食べ物のことも指します。
パンの始まり
人類は農耕や農業を始めるより早く、狩猟採集時代からすでに野生の「大麦」や「小麦」、「カラスムギ(オーツ麦)」などを採取・粉砕をしてパンを焼いていたと言われています。その証拠にヨルダンでは、約1万4400年前の暖炉跡から「ピタパン」のようなパン屑のようなものが発掘されており、ほかの遺跡でものそれに近いものが確認されています。
本格的にパンを作り始めるようになったのは、約6000年前の「古代エジプト」でここで「発酵」という技術を使用してガレットのような「平焼きパン」を焼くようになりました。これが世界最古のパンだと言われており、現在形を残している最古のパンはスイスの「トゥワン遺跡」で発掘された紀元前3500年前後に小麦粉だけで作られた、重さ250g、直径17㎝のパンで、上部が膨らんだ「丸型」のパンだと言われています。
その時代にはすでに、今の原型に近いものを口にしていたことがわかります。
パンと「ヨーロッパ」
エジプトでパンが確立された後、ギリシャを経てローマに伝えられたとされています。古代ヨーロッパでは、パンの製法には大きな変化はなく、ローマ帝国が各地を征服していく中で「パン食文化」もヨーロッパ各地に伝えられていきました。
変化が起きたのは「中世ヨーロッパ」で、大麦から作られていたパンが次第に「小麦」を使ったパンが主流となり、一部の地域(ドイツや北欧)では「ライ麦粉」をを使用したパンが作られるようになりました。そして「飢饉」の際にさらに混ぜ物の量が多くなったとされています。
パンと「日本」
パンが日本に伝わってきたのは「安土桃山時代」だと言われています。天分12年(1543年)に種子島に漂着したポルトガル船によって「鉄砲」の伝来とともにパンが伝わったとされています。ちなみに日本で最初のパン屋は肥前国松浦軍平戸でイタリア人が開いたと言われています。
その後、「キリシタン禁教令」によってパンの製造も禁止され、長崎の出島で細々と伝承されていきました。
日本でパンが本格的に作られたのは江戸時代の末に「江川英龍(太郎左衛門)」が「兵糧」としてのパンの有用性に着目し製造を開始したと言われています。
その後、様々な時代を経て「あんパン」や「総菜パン」の発明や学校給食におけるパンの消費が始まり、2011年には1世帯当たりのパンの購入金額が史上初めて米を上回りました。
まとめ
今回は「パン」とその歴史についてお話しさせていただきました。
その時代の変化によって食べ物も変化・発展していることに改めて勉強させられることが多かったなと感じました。
皆さんも「パンの歴史」を感じながら食べていただけると幸いです。

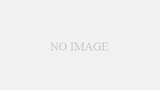
コメント