不定期で投稿する好きなようにブログを書く「ちょっとした雑談という名の『独り言』」の回が始まりました。
今日の独り言は、9月17日といえば「十五夜」ですね。ススキやお団子を飾ってお月見をするという風習なのですが、この「十五夜」の歴史はご存じでしょうか?ちなみに私は知りませんでした。
この十五夜という風習は、昔の「中国」の習慣が元になっているようです。中国の「唐代」(618~907年頃)から中秋節が盛んになったようで、身分に関わらず街を挙げて夜通し騒いでいたと宋の時代に書かれた書物に記されています。また、明の時代に書かれた書物には、「宴会」に加えて名月の日に「供え物」や「月餅(中国の菓子)」を送りあう習慣が始まったと記されています。
日本に伝わったのは「平安時代」の貴族社会において「八月十五夜の宴」を開いたと当時の文献に記されています。当時の日本の月見は、「詩歌」や「管絃」を使用した演奏を楽しみつつ「酒」を嗜む催しで、庶民には縁がなく、催しといっても当時の中国や日本では、ただ月を眺めて楽しんだとされており、日本の「竹取物語」においてはそのような場面があり、当時の風潮が描かれています。
その後、室町時代では宴としては簡素となり、後期で「月に拝んで供物を供える風習」が生まれました。このころにお供えされたいたものは、「枝豆」「栗」「柿」「瓜」「ナス」「芋」「粥」などで、特にナスは、あけた穴から月を見て祈る祝儀「名月の祝」の様子が当時の書物に記されています。
江戸時代になると、当時の中国の風習に習い「団子」を供えるようになりました。ただし、前期の記録によると十五夜の日は「芋煮」を食べて夜遊びをすることが一般的だったらしく、庶民が団子を供えた記録が残されていません。家庭で供物の習慣が始まったのは中期からで、後期になると十五夜の日は文机(ふづくえ)で祭壇を準備して、供え物として月見団子を供えたと記録されています。ちなみに江戸では「球形」、京阪では「サトイモの形」をしたものを供えたとされています。
ススキを飾るのは江戸時代において、「武蔵野・江戸」から「東北」にかけて行われた習慣でしたが、明治以降に全国的に広まりました。
ところで「十五夜」という言葉は、2つの場合があります。「月齢15日目」を指す場合と「月見行事の十五夜」を指す場合です。旧暦では「毎月15日」が月齢15日目の十五夜となっています。そして月見行事をする十五夜は、旧暦「8月15日」を指し、「十五夜」と「中秋の名月」は同じです。
旧暦では7~9月が秋になりますが、秋の真ん中の中秋は、空が澄み渡り月が最も美しく見えることから旧暦8月15日の十五夜を「中秋の名月」と呼んで月見をするようになったそうです。新暦になった今でもこの名残が残っているため「中秋の名月」の日にお月見をするようになっています。
いかがだったでしょうか?毎年当たり前のようにやっている「十五夜」ですが、長い歴史と変革があったことに驚きでしたね。私も十五夜の日にはなるべく月を見るようにはしていますが、なにぶん実家暮らしで周りが山なので見えないことがしばしばあります。今年は、見えたらいいなと胸の内に秘めながら、今回の「独り言」を終わりにしたいと思います。
また、次回の「独り言」でお会いしましょう。それではまた次回!

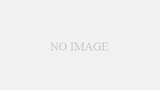

コメント